「“っ”ってどう読むの?」「“や”と“ゃ”って違うの?」 そんな疑問を持ったことはありませんか?
お子さんが言葉を話し始めたり、文字に興味を持ち始めると、 「小さな“っ”って何?」「この文字だけ小さいのはなぜ?」という疑問が出てくることがあります。
拗音(ゃ・ゅ・ょ)や促音(っ)は、大人にとっては当たり前でも、 子どもにとってはまだまだ未知の世界。 耳で聞いて、口でまねして、目で見て、少しずつ「ことばのしくみ」を感じ取っていく中で、 小さな文字の役割はとても複雑で、最初の“つまずきポイント”になることもあるんです。
例えば、「やま」と「しゃま」、「つき」と「ちっき」など、 たった一文字の違いで、音も意味もがらりと変わってしまいますよね。 でもその変化を「おもしろい!」と感じられるようになれば、 言葉の世界がどんどん広がっていきます。
この記事では、そんな言葉の冒険の第一歩を、 おうちで楽しく・やさしくサポートするためのアイデアをご紹介します。
親子で笑いながら「言葉っておもしろいね」と感じられるように、 遊びながら取り入れられる工夫や年齢別のアプローチをお届けしていきます。
焦らず、でも着実に。 お子さんのペースを大切にしながら、一緒に進んでいくためのヒントになれば嬉しいです。
よくあるつまずきとその原因
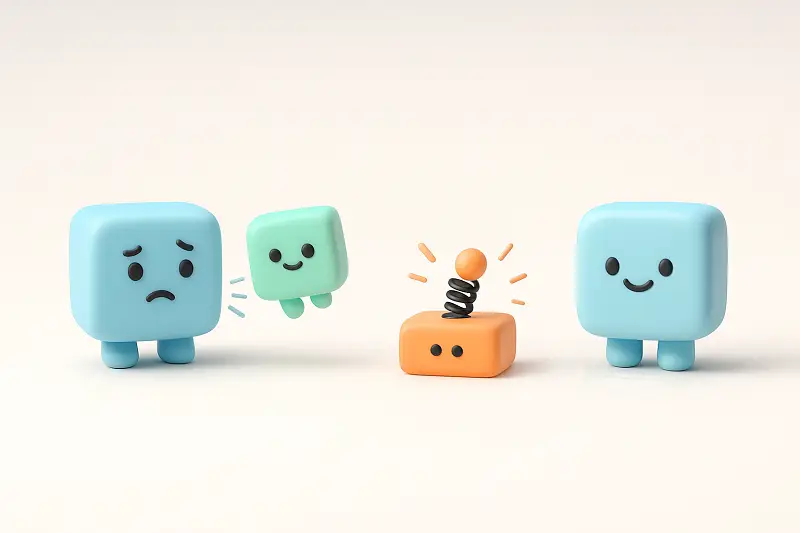
「ゃ・ゅ・ょ」「っ」って何が難しいの?
小さな文字は見た目も分かりづらく、発音の変化もあるため、 初めて出会うお子さんにとってはとても難しく感じられます。 大人にとっては自然にできる発音でも、子どもにとってはまだ耳や口の発達途中。 聞こえ方や真似の仕方にも個人差があるんです。
特に「ゃ・ゅ・ょ」は、前の文字と組み合わさることで音が変化し、 単語の意味も変わってしまうため、「普通の“や”と何が違うの?」と戸惑うことが多いです。 たとえば、「きやく」と「きゃく」では全く意味が違いますよね。 このような“ちょっとした違い”を理解するのは、幼児にとってハードルが高いのです。
また、「っ」は発音そのものが“間”や“詰まり”を表すため、 聞き取りづらかったり、発音しにくかったりすることがあります。 「はっぱ」や「きって」など、普段の会話でもよく使われる言葉の中にあるため、 間違って覚えることも少なくありません。
どの年齢で自然に覚えるの?
拗音や促音を自然に理解できるようになるのは、 多くの場合5〜6歳ごろからが目安とされています。 この時期になると、耳で聞いた音と、目で見る文字を結びつけられるようになり、 「小さい文字があると音が変わる」という概念を少しずつ理解し始めます。
ただし、子どもの発達には個人差が大きく、 3歳ごろから「なんか違うな?」と気づく子もいれば、 小学校に入ってから急に「わかった!」と腑に落ちる子もいます。
保育園や幼稚園での集団生活、読み聞かせの習慣、 家庭での言葉あそびなど、環境によっても習得のタイミングは変わってきます。 「うちの子だけまだ…」と心配する必要はありませんよ。
親が焦ると逆効果?
「なんでできないの?」「何回言ったら覚えるの?」 そんな風に思ってしまうこと、ありますよね。 でも、拗音や促音は“練習すればすぐできる”というものではありません。 音の微妙な違いを感じ取り、意味の違いと結びつけ、 そのうえで文字として理解する…という複雑なプロセスが必要です。
ですから、焦るよりも「一緒に楽しむ」姿勢がとても大切です。 親御さんが笑顔で関わることで、子どもも安心して取り組めるようになります。 うまく言えたときにはしっかり褒めてあげて、 間違っても「惜しかったね〜」と優しくフォローしてあげてください。
家庭での学びがプレッシャーにならないように、 「遊びながら学ぶ」ことを大切にしていきましょう。
【年齢別】自然な教え方と関わり方
3〜4歳|耳でリズムを楽しむ時期
この時期は、まだ文字の読み書きよりも「音」に対する感覚が鋭く、耳から入ってくる言葉を全身で楽しむ力が育つ大切な時期です。
歌や手遊び、絵本の読み聞かせを通して、「ことばって楽しい!」と感じられる経験を積み重ねていきましょう。 特に、リズムや繰り返しのある言葉遊びは、自然と「小さい“っ”」の感覚につながっていきます。
たとえば…
- 「がっしゃーん!」「ぴょんぴょん」「どっしーん」など、擬音を使った遊びを親子で声に出して楽しむ
- 「おにぎり ぎゅっぎゅっ」「きゅうきゅうしゃ」「しゃっくり」など、体を使って言葉の音を真似る遊び
- 絵本の中で見つけた拗音や促音を、指でなぞって「ここ、ちっちゃい“っ”だね」と声に出す
こうした活動を通して、文字に入る前の「耳と口の準備」が整っていきます。
4〜5歳|音の違いに気づく時期
4〜5歳になると、音の違いに少しずつ気づけるようになります。 耳で聞いた言葉の中から、「なんか違う音がする!」と反応できるようになるのが、この時期の大きな成長ポイントです。
「や」と「ゃ」のような似た音の区別も、遊びを通じて感覚的に学んでいくことができます。 この時期は、文字への興味が出始める子も多く、ゲーム感覚での言葉あそびがとても効果的です。
遊び例:
- 「やさい」「きゃべつ」「ゆき」「しゅくだい」など、言葉の中に入っている小さな文字を聞いて見つけるゲーム
- 大きい「や」から始まる言葉、小さい「ゃ」が入る言葉を分けてみる遊び(カードを使ってもOK)
- 絵本や図鑑を見ながら、「どこに小さい文字があるかな?」と親子で一緒に探してみる
音への気づきをほめることで、どんどん自信がついていきますよ。
5〜6歳|文字と音を結びつける時期
5〜6歳は、「聞こえた音」と「見た文字」が一致しやすくなってくる時期。 読み書きへの意欲も高まる中で、拗音・促音を意識する力もぐんと育ってきます。
この頃には、「小さい“っ”が入ると、音が変わるね」「“ゃ”があると“や”とは違うね」といった、具体的な言語理解が芽生えてきます。 遊びの中で何度も繰り返すことが、理解を深める鍵になります。
練習のヒント:
- 拗音・促音が出てくる絵本や言葉あそびの絵カードを使って、正しい言い方と文字の形をセットで意識する
- なぞり書きプリントを使って「ちっちゃい“ゃ”って、こう書くんだね」と声に出しながら練習
- 自分の名前や家族の名前の中に、拗音や促音があるか探してみる(例:さっちゃん、きょうこ、しゅんた)
できたときには、しっかりと褒めてあげることで「もっとやりたい!」という気持ちにもつながります。
お子さん一人ひとりのペースに合わせて、楽しく続けられるように工夫してみてくださいね。
家庭でできる楽しい言葉あそび

おでかけ中もチャンス!
お買い物や公園に行ったときも、言葉遊びのチャンスはたくさんあります。 身近な風景の中で、小さな文字に注目することで、自然に学ぶ習慣が育ちます。
- 「にんじん」「じゃがいも」「きゃべつ」など、八百屋さんの野菜から小さい文字を探すゲーム
- 公園で見つけたものを使ってクイズ形式に。「きっぷ」「しゃぼんだま」「すなば」など、音の中にある小さな“っ”や“ゃ”を聞き取れるかな?
- 看板や広告、カフェのメニューの中から、「ゃ・ゅ・ょ」「っ」のついた言葉を親子で交互に見つける競争ゲームもおすすめです
たとえば、「この中に“っ”がある言葉、どれかな?」と声かけするだけで、子どもは意識し始めます。 自然な会話の流れの中で「気づき」を促すことで、無理なく理解が深まります。
さらに、お友だちや兄弟と一緒に遊ぶと、より楽しく盛り上がりますよ。
お風呂・食事の時間も活用
毎日ある「お風呂」と「ごはん」の時間は、実は最高の学びタイムです。 親子でゆったりとした時間を過ごせるからこそ、言葉に触れる良いきっかけになります。
- お風呂の壁に貼れる文字ポスターで、拗音・促音のある言葉を探す (「しゃぼん」「きゅうり」「がっこう」などを指さして読み上げる)
- お湯に浮かべて遊べる50音のパズルを使って、「小さい“っ”が入る単語作ってみよう!」と声かけ
- 食卓では、献立の中から言葉探し。「きゃべつ」「しゃけ」「ハンバーグ」など、身近な料理にたくさんの小さい文字が隠れています
加えて、「どんな音が入ってたかな?」と食後に振り返るのもおすすめです。
無理に「勉強」として取り入れるのではなく、親子の楽しい会話の中にちょっとずつ加えていく。 それだけでも、お子さんの中に確実に“ことばの感覚”が育っていきます。
大切なのは、正しくできることより「気づけたこと」「楽しめたこと」なので、 たとえ間違えても、笑顔で「いいところに気づいたね」とほめてあげましょう。
おすすめ学習ツール紹介
絵本・カードで楽しく学ぶ
拗音や促音に親しむには、音のリズムやイメージが自然に入ってくる絵本やカードがとても効果的です。 お子さんが自分から「読んで!」と言いたくなるような、おもしろくて繰り返し読みたくなる教材を選びましょう。
- 『あっちゃん あがつく』:リズミカルな文章で文字と音の世界を楽しめる定番絵本。遊びながら五十音に親しめます。
- 『ことばあそびえほん』シリーズ:拗音や促音が自然に出てくる言葉がたくさん登場。繰り返し読むことで音に慣れていけます。
- 拗音・促音専用の知育カード(◯◯リンク紹介可):絵とセットになっていて視覚的にもわかりやすい!親子でクイズ形式にも使えます。
- お風呂ポスタータイプの教材:毎日目に入ることで、自然と小さい文字の存在を意識するようになります。
音をまねしたり、声に出したりする遊びと組み合わせると、より効果的です。
無料アプリでスキマ時間に
忙しい毎日の中でも、ちょっとした時間に楽しく学べるのがアプリの良いところです。 飽きさせない仕掛けがたくさんあり、ゲーム感覚で取り組めるので、お子さんも喜んで使ってくれるはずです。
- 拗音・促音に特化した読み書き練習アプリ:一文字ずつなぞったり、読み方を当てたりしながら、自然に学習できます。
- かわいいキャラクターが登場する知育アプリ:ごほうびがもらえたり、ステージクリアで達成感が味わえたり、やる気を引き出してくれます。
- タイマー設定や保護者用機能があるアプリなら、使いすぎも防げて安心です。
どの教材を選ぶときも、「楽しい!」「わかる!」という気持ちを大切に。 レビューや口コミだけでなく、お子さんの性格や好みに合うかどうかも見てあげてくださいね。
よくあるお悩みQ&A
Q:「まちがって発音してるけど、直したほうがいい?」 →まずは否定せず「こう言ってみようか」と寄り添ってあげてください。 子どもは“まちがい”を指摘されると、やる気をなくしてしまうこともあります。 代わりに、お手本となる発音をやさしく聞かせてあげたり、遊びの中で正しい発音に触れさせたりすることが効果的です。 「上手に言えたね!」と、うまくできた瞬間を逃さず褒めると、次への意欲につながります。
Q:「何回言っても覚えられない…」 →子どものペースを信じて。繰り返しと“楽しい”が鍵になります。 一度で覚えられないのは当たり前です。 それよりも、「何度も触れているうちに少しずつ慣れてきたね」と、進歩を見つけてあげましょう。 歌や絵本、遊びなどバリエーションを変えて繰り返すことで、自然に身についていくことが多いですよ。
Q:「他の子と比べてしまって不安です…」 →その子のタイミングがあります。焦らなくて大丈夫ですよ。 発達のスピードには個人差があります。 同じ年齢でも、言葉の理解が早い子・ゆっくりな子、いろいろです。 「比べるより、その子の成長に寄り添う」ことが大切です。 うまくできたことを一緒に喜ぶことで、親子の関係もぐっと深まりますよ。
まとめ|一緒に楽しむ気持ちが一番の近道

拗音・促音は、確かにつまずきやすいポイントです。 文字が小さかったり、音が変化したりと、大人にとっては当たり前のことでも、 子どもにとってはひとつひとつが新しい発見であり、難しく感じる瞬間でもあります。
でも、だからこそ焦らず、比べず、「一緒に楽しむ」気持ちがとても大切です。 「こう発音するんだよ」ではなく、「一緒に言ってみようか」と寄り添いながら、 遊びや生活の中に自然に取り入れていくことで、 子どもは安心して学びに向かうことができます。
できたときには、「すごいね!」「今の上手だったよ」と、 小さな成功体験をたくさん積み重ねてあげてください。 それが「もっとやってみたい!」という意欲を育て、やがて自信となっていきます。
そして何よりも、お子さんと一緒に過ごす日常が、 かけがえのない学びの場であることを、どうか忘れないでください。 一緒に笑って、つまずきも楽しんで。 そんな時間こそが、子どもにとって最高の学びにつながります。
お子さんとの毎日が、やさしくあたたかな学びの時間になりますように。 このページが、その第一歩になれたらとても嬉しいです。


